フリースクールとは
不登校の子どもたちのため
居場所作りと社会的自立を支援
フリースクールとは
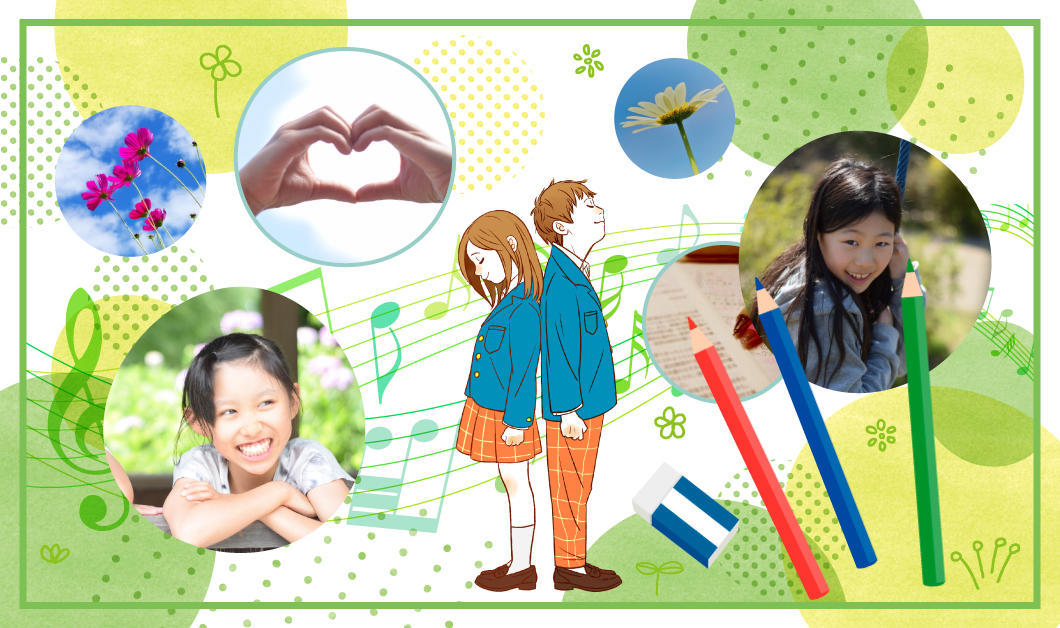
友人関係のトラブルや学習面の不安、身体的な事情など、さまざまな理由で学校に通えない児童・生徒たちにとって、社会との接点を持てる場所はとても大切です。そのひとつの選択肢として注目されているのが「フリースクール」です。公的な機関ではありませんが、義務教育期間中はフリースクールへの登校が"在籍校への出席扱い"になることもあります。また、中高生にとっては、全日制・定時制・通信制といった正式な学校に入学・復帰するための一歩を踏み出す場としても、フリースクールは重要な役割を担っています。
地域の小中学校とも連携
義務教育期間中は"在籍校の出席扱い"に
全国に500近くある「フリースクール」は、不登校や引きこもりの子どもたちの精神的なサポートを行いながら、学習意欲の回復を応援する場所です。医療機関と連携している施設、自宅でサポートを受けられる施設、学習障害や発達障害のある人などを受け入れている施設などもあり、いずれもNPO法人やボランティア団体など民間の教育機関が運営しています。 フリースクールは学校教育法上で公的に認められた学校ではありませんが、地域の小中学校と連携しているケースが多く、義務教育期間中(※)は在籍校の校長が認めた場合、フリースクールへの登校が"在籍校の出席扱い"になります。 基本的に入学資格は設けられておらず、施設の規模や方針にもよるので一様ではありませんが、月会費の相場は3万円程度が目安とされています。
(※)高校生は義務教育ではないため、フリースクールに登校しても出席扱いにはなりません。
カウンセリングや個別・少人数学習で
精神面の安定、学習意欲の回復を応援
フリースクールとよく比較される施設に「サポート校」がありますが、基本的にサポート校は通信制高校に通う生徒の学習支援を行うところです。どちらかというと学習塾の色合いが強いサポート校に対し、フリースクールは学校に行けない児童・生徒の"居場所"となり、生活面や精神面を支援することに軸足をおいているのが特徴です。
多くのフリースクールでは、その日その日の活動内容は本人に委ねられ、子どもたちは好きな教科の勉強をしたり読書を楽しんだりと、自由に学習を進めることができます。
体験学習やシーズンごとの行事、レジャー活動など、施設に通う子ども同士が交流を深める機会を設けている施設も少なくなく、進路や悩みを相談できるスタッフ、自分と似た境遇の仲間との交流を通じ、子どもたちは社会的自立を目指します。

フリースクールは、正式な学校復帰への第一歩
通信制高校への進学パターンが多数
『令和2年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について』(文部科学省)を基に作成。
なお、文部科学省発表のデータ(※)によると、不登校を理由とした長期(30日以上)欠席者数は年々増加傾向にあり、令和2年度の不登校児童・生徒数は全国で、小学校6万3350人、中学校13万2777人。不登校で悩む子どもが、もはや特別な存在でなくなりつつある昨今、その不安や焦りを解消するための居場所を用意することが、ますます大切になってきています。
一歩ずつゆっくりと踏み出したい、マイペースでもいいから無理せずに頑張りたい、そう考えている不登校の子どもにとって、フリースクールは心の負担を和らげ、自信と元気を取り戻せる場所であることは間違いありません。実際、不登校の中高生の場合、フリースクールから通信制高校に進学・復帰して高卒の資格を目指すパターンが多いようです。
学校に復帰することだけが重要なことではありませんが、その後の選択肢も視野に、まずは本人にとっていま必要な"居場所"をみつけてあげたいですね。
情報あつめの第一歩!


一口に「高校」といっても種類はさまざま。まずは、いろいろな高校のカタチを知ることから始めてみましょう!
特に通信制高校は、これまでの常識にはあてはまらない新しい教育スタイルを次々と打ち出し、大きな注目を集めています。だからこそ、それがどんなものかを知ることはとても大きな一歩になります!
ホームページで調べるほかにも、学校説明会やオープンキャンパスに参加して学校の雰囲気を肌で感じることも、情報集めにはとても有効です。「どんな高校生活を送れるんだろう?」ということはもちろん、「その先どんな大人になれるんだろう?」という視点で見聞きしてみることが、情報集めのポイントですよ!
おおぞら高等学院は、なりたい大人になるための一人ひとりの頑張りを全力で応援しています。学校説明会や個別相談は全国各地で開催中です。もちろんオンラインでの開催も行っておりますので、お気軽にどうぞ!
